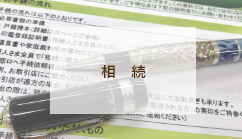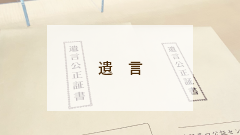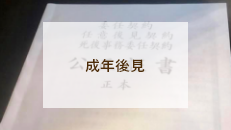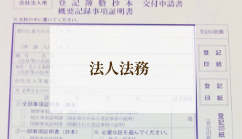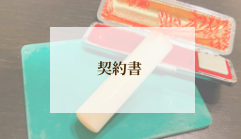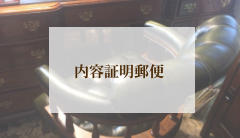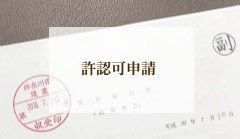ご相談者・ご依頼者とのご縁を
お悩み事に寄り添い、紡ぐ。
あなたの街、あなたの海の法律家。
遺言
遺言とは
遺言(ゆいごん,いごん)とは、自己の財産を,自己が死亡した後に最も有効かつ有意義に活用するため,死後の法律行為を定める遺言者の最終意思の表示です。
遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こる例が多々ありますが,このような争いを未然に防止するために,遺言者自らが,自己の財産の帰属を決定することに主な目的があります。なお,非嫡出子を認知する等の法律で定められた身分上の事項も定めることができます。
遺言書を作成するのが望ましいケース
遺言書を作成することにより,様々なトラブルを未然に防ぐことができ,また自分の生前の意思を遺族に対して伝えることができます。
次のいずれかに該当する場合には,遺言書を作成することをお勧めします。
1
夫婦に子がいない場合
相続人は,配偶者だけではありません。被相続人に子がいない場合の配偶者以外の血族相続人の相続権の順位は,①直系尊属,②兄弟姉妹です(民法889条1項参照)。長年連れ添った配偶者にすべての財産を残したい場合には,遺言が有効です。
2
特定の相続人に相続させたい場合又はさせたくない場合
例えば,配偶者に対して住居を相続させたい場合,身体障害者の子・未成年の子に多くの遺産を相続させたい場合,老後の世話をすることを負担として子に多くの財産を相続させたい場合,不義理な子に相続させたくない場合,先妻の子に相続させたくない場合などです。
これらの場合には,遺留分(同法1042条以下)に注意する必要があります。
3
相続人がいない場合
特別縁故者(例.内縁の妻等)が存在しない限り,遺産は,国庫に帰属します(同法959条)。
したがって,この場合には,特にお世話になった人に遺贈したり,寺院・教会・社会福祉関係の団体・自然保護団体・各種研究機関などに寄付したりするときには,遺言をしておく必要があります。
4
行方不明の相続人がいる場合
家庭裁判所に対し,不在者財産管理人を選任(同法25条)する必要,又は失踪宣告審判の申立てをする必要(行方不明者の生死が不明な場合,同法30条)が生じます。
5
再婚している場合
先妻の子と後妻がいる場合には,両者間には,元々,感情の対立があります。父(夫)が生存している間は,その感情は潜在化していますが,死亡した途端に顕在化し,遺産を巡って激しい対立が生じる傾向があります。
6
お世話になっている人(例.子の配偶者,子がいる場合の兄弟姉妹等)や相続人以外の親族(例.長男の嫁,孫,甥,姪等)に遺贈したい場合
これらの人は,法定相続人ではないため,遺言がないと相続権がありません。また,口約束のみでは,争いが生じるケースが多いです。
7
内縁の妻がいる場合
いわゆる妾のことだけではなく,何らかの事情により婚姻届が提出されていない事実上の妻も含みます。内縁の妻には,原則として,法律上の相続権はありません。
8
施設・団体等に寄付をしたい場合
9
遺産が事業用財産・農地の場合
均分相続にはなじまないため,無理に分割すると経営が破綻する場合が多いので,事業の承継・維持のためには,遺言が有効です。
10
葬式の方法に特別な希望がある場合
例えば,親族のみによる密葬,香典・供物・供花の辞退,特定の宗教による葬式などです。
11
ペットの世話を第三者に依頼したい場合
共同遺言の禁止
遺言書は,夫婦など二人以上の者が同一の証書ですることができません(共同遺言の禁止,民法975条)。
遺言書を発見した場合
遺言書が公正証書遺言以外の場合には,遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,相続の開始を知った後遅滞なく,遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認の申立てをしなければなりません(家事審判法9条1項甲類34号参照)。そして,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人などの立会いの上,開封しなければなりません(民法1004条)。
なお,遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられますので(民法1005条),ご注意ください。
遺言の撤回
遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。